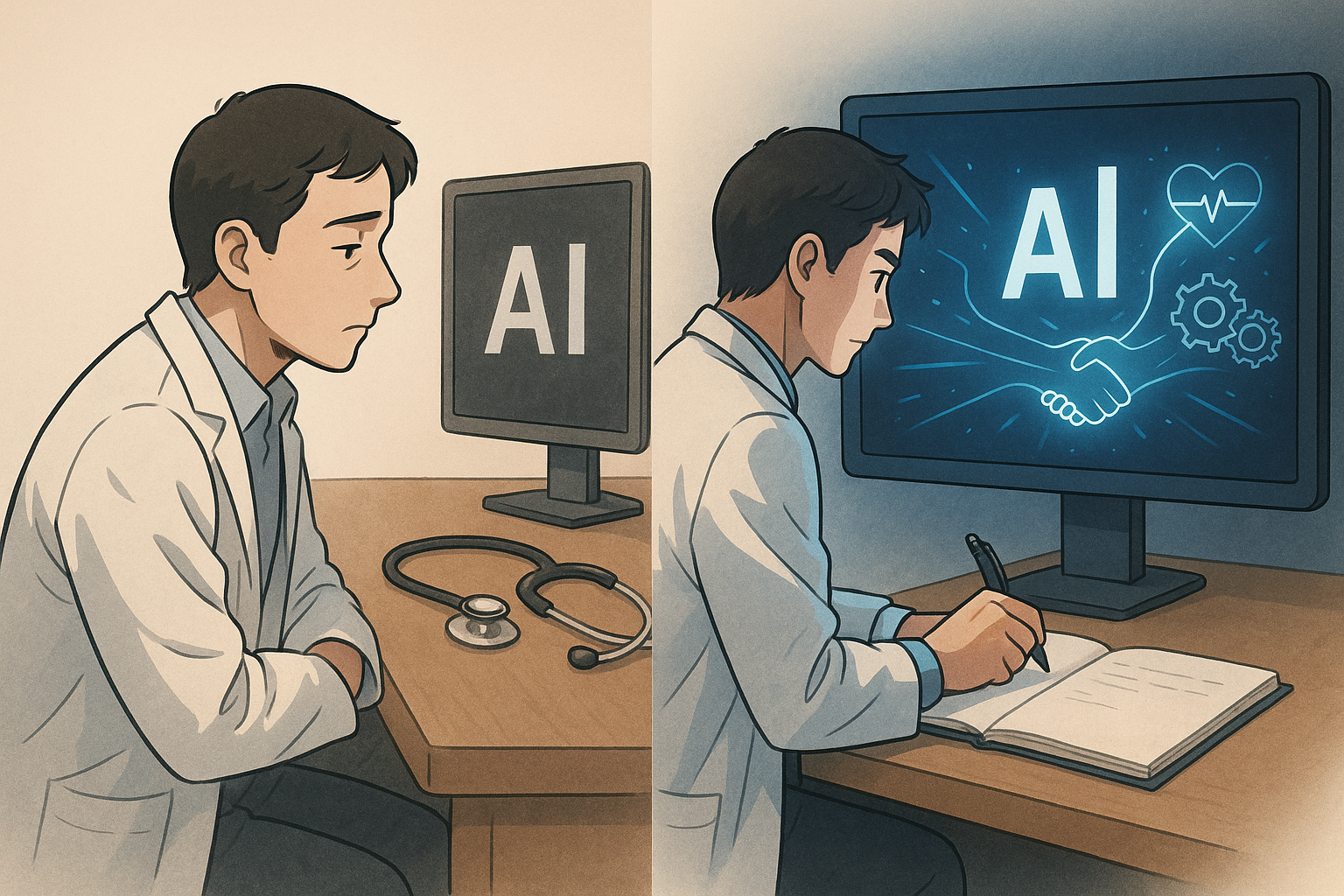2分で読める「生成AIのいま」Vol.23 「AIによって人間のスキルが下がるのであれば、AIは人間にとって良くないのか?」
- 生成AIについてやさしく学べるブログシリーズ。今回も読みごたえのある内容になっています^^。
「最近の医療論文から見る、今後のAIと人間の関係」について、先日も解説したHuman AI Interactionの観点から考察してみました。
======
医療田:
ねえねえ、機械屋さん。
機械屋:
何でしょう?
医療田:
この前、Human–AI Interaction(HAI)の話をしたじゃない?
そのあと、この論文を見つけたのよ。Lancetっていう、医学では有名な学術誌があって、
その関連誌 Lancet Gastroenterology & Hepatology に出てたんだけど……。
Budzyń K, et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2025 Aug 12:S2468-1253(25)00133-5.
"Endoscopist deskilling risk after exposure to artificial intelligence in colonoscopy: a multicentre, observational study"
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40816301/
機械屋:
どれどれ。――なるほど。「AIによる医師のデスキリング(技能低下)」についての論文ですね。
医療田:
そうなんだよ。
1. 論文の要点
機械屋:
AIを使い始めた医師の検査能力が落ちてしまった、というやつですね。
医療田:
そうそう。
ポーランドの4施設での大腸内視鏡を対象にした観察研究。
「AIによる診断支援を導入後、AIなしでの成績をを導入前と比較したら、
腺腫(大腸ポリープの一種)の検出率が、28.4%から22.4%へ、絶対で約6%低下した」
んだって。
機械屋:
つまり、AIに慣れた後では、AIなしだと“見逃し”が増えてしまったと。
まさに、「de-skilling」ですね。
医療田:
AIが便利になるのはいいけど、頼りすぎると腕が鈍っちゃう、ということだよね。。
なんとなく予測はしていたけど。
2. HAIの視点でどう考える?
機械屋:
では、この研究報告を、HAIの論点から考えてみたいと思います。
医療田:
お願いします!
機械屋:
先日、時代に伴う人とAIの関わり方、つまりHAIは
人間がAIにとっての「操作者→協働者→監督者→委任者」と変化していく、と話しましたよね。
医療田:
うんうん。
機械屋:
でも今回の論文が示すのは――AIの登場によって、人が自ら経験を積む時間が減り、スキルが痩せ細ってしまうという危険です。
医療田:
そうだね、
機械屋:
これは、言い換えると、
「HAIのデザインを誤ると、人間が弱くなる。」
こういうこともできますよね。
医療田:
あっ、なるほど…
…わかった気がする。
この話、
「AIはよくない!」とか「AIを使うと人間はだめになる!」という、、
機械屋:
そうなんです。
そういう短絡的な話ではない、ということですよね。
3. 教訓とAIデザインの未来
機械屋:
AIは「便利なツール」です。
ただ、そのツールにたよると、人間の能力が衰える。
いわば「車に乗ってばかりいたら足腰が弱くなる」というような状態ですね。
医療田:
そうね、、
「人間の足腰が弱くなったのは車のせいだ!」と言ってしまうと、
大事なものを見失いそうだよね。。
機械屋:
その通りです。
医療田:
例えば――
・AIの結果を必ず人間が二重チェックする
・若手にはAIなしでの経験を必ず積ませる
・AIがどうしてそう判断したかについて思考する
――ちょっと月並みかもしれないけど、
こうした工夫が不可欠だよね。
機械屋:
その通りですね。
しかもこれらは単に「なるべくそうするように努める」ということでは不十分で、
AIとの協業する環境、職場でも家庭でもいいですが、そこにこういった「望ましいHAIが実現されるための工夫」が、
デザインとして盛り込まれている必要がある、ということでないかと思います。
医療田:
つまり、AIを使いながらも“人が考える余地”を、システムとして残す、
AIをそんな風にデザインする、ってことかな。
機械屋:
はい。その通りです。
以前、HAIの具体的な尺度について、お話したと思うのですが、
医療田さん、覚えてますか?
医療田:
覚えてない、、
けど、確かメモを取ってたな。
あ、これだ:
● 信頼性(Reliability)
● 説明可能性(Explainability)
● 人間中心設計・人間拡張(Human-Centered Design & Augmentation)
● AIと人間の協調性(Collaboration)”
● AIの目標を人間の意図や社会的価値観に合わせる”アラインメント(Alignment)
機械屋:
そうです。
この中で、AI設計のゴールとしては"人間中心設計・人間拡張"の部分が大事になり、
その他の尺度は、設計の際の重要なマイルストーンになると思われます。
HAIの視点から見れば、
"「AIで人の能力を補完する」とか、「AIで人の生活の幸福度を上げる」ことが、
AIの本質的な役割である"、ということになります。
昨今のAI、その進歩の速度は目覚ましいですが、望ましいHAIの在り方、AIのデザイン論については
まだまだ、これからではないかと思われます。
4. (余談)過去の産業史と合わせて考えてみる
機械屋:
ちなみにですが、医療田さん。
医療田:
なになに?
機械屋:
新しい技術によって、人間のこれまでの能力に大きな影響が出た、というのは、
なにもAIが初めて、ではないですよね。
医療田:
うん、私もそう思ってた。
機械屋:
産業史を振り返ると、
「新しい技術が登場するたびに、ある技能は衰え、別の力が伸びた」
そんなことが繰り返されてきたように思います。
たとえば、
蒸気機関が出てきたとき、重い荷を運ぶ“剛力”は要らなくなりました。
でもその代わり、人間の移動距離は飛躍的に伸び、経済活動の幅も広がりました。
医療田:
そうだよね。
蒸気機関とか、電気が出る前の人たちって、
屈強な人たちは、さぞ頑丈だったんだろうな、って思うよ。
あ、あと、
計算とか、字を書く能力とか。
うちの死んだおばあちゃんとか、字がすごいきれいだったもん。
今でも手紙、取っておいてあるよ?
機械屋:
そうなんですね、いや、それは素敵なお話で、、心温まります。
医療田:
ありがとう、また話の腰、折っちゃってごめん。
機械屋:
いえいえ、、
計算機やワープロの登場で、暗算や字を書く力は衰えたかもしれない。
でも全体の知的生産スピードは格段に上がったはずです。
医療田:
つまり、
「歴史の転換点で
我々は何かを失い、けれども同時に何かを得てきた。」
そういうことかな。
機械屋:
その通りですね。
AIによって一部の技能が減っても、人間全体の生産性や可能性が広がるなら、それは、
我々がこれまでも経験してきた、技術進化の歴史の一貫、なのかもしれません。
いずれにせよ、最適なHuman AI InteractionのためのAIデザインは、まだまだ、これからが正念場と言えそうですね。
======
●関連記事
・2分で読める「生成AIのいま」Vol.19 Human AI Interaction (HAI) - AIの最適利用を目指して
https://www.youichimachida-ai.com/blog/2aivol19human-ai-interaction-hai-ai
・2分で読める「生成AIのいま」Vol.20 - AIの進化によってダイナミックに変化するHuman AI Interactionについて
https://www.youichimachida-ai.com/blog/2aivol20-aihuman-ai-interaction
●2分で読める「生成AIのいま」シリーズ。バックナンバはブログからどうぞ!
https://www.youichimachida-ai.com/blog